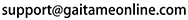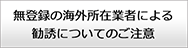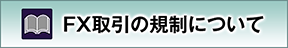「トランプ大統領、通商法122条を適用か」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- ドル円は不透明感が増し方向感が出ない中、米金利が低下したことで155円近辺から小幅に下落。
- ユーロドルは小幅に反発し、1.18台に乗せる。
- トランプ関税を巡る不透明感から前日買われた株式は主要3指数が揃って大幅に下落。ダウは821ドル下げ4万9000ドルを割り込む。
- 市場に不安が高まったことで債券は買われる。長期金利は4.03%台に低下。
- 金は大幅に続伸。原油は小幅に続落。
12月製造業受注 → −0.7%
12月耐久財受注 → −1.4%
****************
| ドル/円 | 154.23 〜 154.94 |
|---|---|
| ユーロ/ドル | 1.1778 〜 1.1810 |
| ユーロ/円 | 181.99 〜 182.59 |
| NYダウ | −821.91 → 48,804.06ドル |
| GOLD | +144.70 → 5,225.60ドル |
| WTI | −0.17 → 66.31ドル |
| 米10年国債 | −0.052 → 4.031% |
本日の注目イベント
- 露 ロシアのウクライナ侵攻から4年
- 米 12月S&P Cotality CS20−City YoY NSA
- 米 12月FHFA住宅価格指数
- 米 2月リッチモンド連銀製造業景況指数
- 米 2月コンファレンスボード消費者信頼感指数
- 米 トランプ大統領、一般教書演説
- 米 コリンズ・ボストン連銀総裁、開会挨拶
- 米 グールズビー・シカゴ連銀総裁講演
- 米 クック・FRB理事講演
- 米 ボスティック・アトランタ連銀総裁講演
- 米 ウォラー・FRB理事、基調講演
本日のコメント
「Tariff Man」・・・。ニックネームでそう呼ばれているトランプ大統領。米国を再び偉大な国にするには、輸入相手国への関税を引き上げることが最善策と考えているようです。
トランプ関税を巡る報道一色です。米連邦最高裁は20日、米国が各国・地域に課した相互関税などを「違憲」とする判断を下しました。判決は9人のうち6人が「違憲」とし、驚いたのはロバーツ長官を含む保守派の3人が「違憲」とする判断を下したことです。トランプ氏も、これには驚いたことでしょう。「飼い犬に噛まれた」とは、このことです。トランプ氏は判決後、「米国にとって正しいことをする勇気を持てなかったことを恥ずべきだ」とコメントしていました。ここまでの動きを市場は好感していましたが、それにひるむトランプ氏ではありません。翌日には「1974年通商法122条に基づき、全ての国の輸入品に150日間限定で10%の新たな関税を課す」と表明しました。122条は、深刻な国際収支の赤字に対応するため、15%を上限に関税を発動することを認めており、トランプ氏は上限の15%を適用するとしています。
関税を巡る動きが再び不透明になってきたことで、金融市場はその行方を読み切れず不安定さを増しています。ドル円は154円前後まで売られた後、155円台まで反発し、154円台半ば近辺で推移しています。株式市場では20日には連邦最高裁の判断を好感し3指数とも買われましたが、昨日は一転して大幅安です。債券も、「違憲」判断で、米国債の増発懸念から一旦は売られましたが、昨日はリスク回避から買われ、長期金利は約2ヵ月半ぶりの低水準まで低下しています。このように、「違憲」判断を受けトランプ氏が今後どのような策を講じるのか不透明感が増す中、ベッセント財務長官は22日、CNNとFOXニュースのインタビューで、「新たな関税は一時的な措置であり、歳入を引き続き財務省に確保するとともに、最終的には別の権限に基づく関税に置き換えられると」述べています。ベッセント氏はCNNに対し、実施前に調査を必要とする他の関税権限に言及しつつ、「議会がどう対応するか見守る必要はあるが、122条は1962年通商拡大法232条や、1974年通商法301条関税の調査が行われる間の『5カ月間のつなぎ』になる可能性が高い」と述べ、恒久的な制度というよりは橋渡し的な措置だと説明しました。またFOXニュースに対しては、122条は「非常に強力な権限だ」とも語っています。
トランプ関税などが最高裁で「違憲」と判断されたことを受け、米民主党の有力議員らは、国民への返金を声高に要求し始めています。ブルームバーグは、「11月の中間選挙を控え、新たなポピュリスト運動が始まった形だ」として、以下のように報じています。「『オハイオ州の各世帯に1336ドル(約21万円)の返金を求める』、とシェロッド・ブラウン元上院議員(民主)は23日、ソーシャルメディアに投稿した。2024年に再選を果たせず、返り咲きを目指す同氏は関税がインフレを招いたとして、対抗馬だった共和党のハステッド議員を、ことあるたびに関税に賛同してきたと批判。『オハイオ州の住民は急騰する物価に苦しんでおり、返金されてしかるべきだ』と述べたと伝え、マサチューセッツ州選出のウォーレン上院議員(民主)は『ドナルド・トランプは違法な関税であなた方のお金を奪った。そして住宅から食料品に至る全ての物価が高くなった』と投稿。『トランプ氏からお金を返してもらうべき時が来た』と主張した。また、2028年に大統領選に出馬するとの観測が持たれているカリフォルニア州のニューサム知事(民主)は『違法なやり方で取られたお金は、直ちに利子を付けて全額返還されなくてはならない』と投稿。『さっさと支払いに応じよ』と続けた。イリノイ州のプリツカー知事も、1世帯当たり1700ドル、総額86億ドルの請求書をトランプ大統領に送った」と、かなり詳しく伝えています。EUも、トランプ政権の関税措置への連邦最高裁の違憲判決を受け、米国が新たに打ち出した関税政策について、「チーズや一部農産物などEUの輸出品に貿易協定で認められている水準を上回る課税が行われることになる」と警告しています。このような動きに対してもトランプ氏はSNSに、「米国を数年、いや数十年にわたって『食い物』にしてきた国などが、ばかげた最高裁の判断をもって駆け引きしようとするなら、はるかに高い関税に直面することになる。こうした国は、最近合意したばかりの協定よりも、悪い取引を突きつけられるだろう。買い手は注意しろ!!!」と、恫喝的な投稿を行い、さらに「自分は大統領だ。議会に関税の承認を求める必要はない」とも述べていました。
トランプ政権の強権は、連邦最高裁をも覚醒させただけではなく、先日行われたカナダに対する課税撤廃でも共和党議員6人が大統領に反旗を翻し、民主党とともにカナダに対する関税の撤廃に賛成しました。ブルームバーグは、「仮に民主党が上下いずれか、あるいは両院で多数派を奪還すれば、トランプ氏が成立を目指すあらゆる法案が頓挫しかねず、政権に対する強力な監視や調査が行われる可能性もある」として、「状況は少しずつほころび始めている。共和党にとっては、トランプ氏中心の政治から一歩距離を置き、有権者へのメッセージを本当の意味で取り戻す好機だと思う。中間選挙で惨敗したくないのであれば、そうする必要がある」と、共和党系ストラテジストのギレスピー氏のコメントを紹介していました。
本日は、トランプ大統領による一般教書演説が予定されています。引き続き強気のコメントが聴かれるのでしょう。
本日のドル円は154円〜155円50銭程度を予想します。
佐藤正和の書籍紹介

これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |

チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 2/17 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「サービス分野のインフレ率が依然として高止まりしている」、「関税に伴う価格上昇が一時的なものであれば、政策当局に行動の余地が生まれる可能性がある」、「これが一時的なものであり、インフレ率が2%へ戻る道筋にあることが確認できれば、2026年に追加利下げが複数回実施される可能性があると考えている。ただ、それを見極める必要がある」 | -------- |
| 2/11 | シュミッド・カンザスシティー連銀総裁 | 「追加利下げを実施すれば、高インフレをさらに長期化させるリスクがあるというのが私の見解だ」、「金利は依然として景気に一定の圧力をかけているはずだが、必ずしもそうなっていない可能性がある。成長に勢いが見られ、インフレが依然として高水準にある中、景気が抑制されている兆候はあまり見当たらない」、「物価圧力は続いており、経済の多くの分野で需要が供給を上回っていることを示している。AIなどの新たな技術革新が将来的に生産性の伸びを高め、インフレを加速させることなく経済成長を可能にする可能性はあるが、まだその段階には至っていない」 | -------- |
| 2/10 | ローガン・ダラス連銀総裁 | 「労働市場に新たな顕著な弱さが示されない限り、金利を据え置くべきだ」 | -------- |
| 2/10 | ハマック・クリーブランド連銀総裁 | 「フェデラルファンド(FF)金利の微調整を試みるよりも、最近の利下げの影響を見極め、経済動向を注視する中では、辛抱強く対応する方が望ましい」、「私の見通しに基づけば、政策金利はかなりの期間、据え置かれる可能性がある」 | -------- |
| 2/5 | ECB声明 | 「経済は厳しい世界環境の中でも底堅さを保っている」、「特に世界の貿易政策を巡る不確実性や地政学的緊張が続いているため、見通しは依然として不透明だ」 | -------- |
| 2/5 | ラガルド・ECB総裁 | 「金融政策のスタンスは今のところ適切だ」、(今回の政策委員会会合でユーロの為替レートについても協議したことを明らかにし)、「ECBは特定の為替レートを目標にしていない」、「ユーロ高が現在の見通し以上にインフレを押し下げる恐れがある」、「インフレ見通しに対するリスクはほぼ均衡しており、ユーロのドルに対する現在のレンジは、これまでの平均的な水準にほぼ一致する」 | -------- |
| 2/3 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「インフレを目標に戻すための最後の1マイルを進む中、これらの利下げは労働市場を支える保険をかけたようなものだと考えている」、「不確実性の後退とともに経済見通しは改善しているとする一方で、人員採用が一部の業種に集中している」、「インフレ率がなおFRBの目標である2%を上回っていることなど、リスクは残っている」 | -------- |
| 2/3 | ミラン・FRB理事 | 「年内を通じて1ポイントをやや上回る規模の利下げを見込んでいる」、「基調的なインフレ率を見ると、経済に非常に強い価格上昇圧力が存在しているとは思えない」、「金融政策を講じなくてはならないような、強い需給の不均衡もあまり見られない。実際の物価上昇圧力そのものというより、主としてインフレの測定方法に伴う特異性によって、金利が過度に高い水準に維持されていると考えている」 | -------- |
| 2/2 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | (自身は利下げを)「1回も見込んでいない」、「経済には非常に強い勢いがあるため、政策金利はやや引き締め的な水準に維持する必要がある。多くの企業の足元のリターンや利益を見ると、現在の金融政策スタンスが極めて、あるいは非常に強く引き締め的だと主張するのは難しい」、「私の見通しでは、利下げを1回ないし2回行えば恐らく中立水準になるだろう。だが、そうすればインフレ率を目標まで引き下げることはもちろん、その軌道に乗せることさえも極めて難しくなる」 | -------- |
| 1/28 | ベッセント・財務長官 | (ドル・円相場への米国の介入について質問され)、「絶対にしていない」、(その可能性について)、「強いドル政策を維持していると言う以外にコメントしない」、「米国は常に強いドル政策を取っている。ただし、それは適切なファンダメンタルズを整えることを意味する」、「健全な政策を実行していれば、資金は流入する」、「米国の貿易赤字が縮小していることを踏まえれば、時間の経過とともに自動的にドル高につながるはずだ」 | ドル円は152円台後半から1円ほど上昇。 |
| 1/28 | パウエル・FRB議長 | 「経済活動の見通しは前回の会合後に明らかに改善しており、これは時間の経過とともに労働需要や雇用に影響を与えるはずだ」、(労働市場については)「安定化の兆しが見られる」、「過度に踏み込むべきではない」、「冷え込みが続いている兆候もある」、(今後の利下げについて)、「次の利下げがいつになるのか、あるいは次回の会合で金利を引き下げるのかについて、明確な判断基準を示そうとしてはいない」、「入手するデータや変化する見通しなどを考慮しながら会合ごとに判断していく上で、われわれは良い位置にあるというのがわれわれの言いたいことだ」、(中央銀行の独立性について)、「独立性の要は政策当局者を守ることではない」、「国民にとって有効に機能してきた制度的な枠組みに過ぎない」、」(任期が終了した後も理事としてFRBにとどまるかどうかの質問に)、「決めていない」 | -------- |
| 1/20 | カーニー・カナダ首相 | 「世界の中堅国は、攻撃的な超大国の強制に抵抗するために協力しなければならない」、「最近の出来事はルールに基づく国際秩序が事実上死滅したことを示しており、カナダやその他の国々は、世界の大国による圧力戦術や威嚇に対抗するため、新たな同盟関係を構築するしか選択肢がない」、「中堅国は協力しなければならない。交渉の席につかなければ、餌食になるからだ」 | -------- |
| 1/15 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「われわれが直面している最も重要な課題は、インフレ率を2%に戻すことだ」、「労働市場に関するこれまでの懸念はいったん後退した。不透明感から企業は採用を鈍らせているものの、大規模なレイオフには踏み切っていない」、「シカゴ連銀の指標は、労働市場が安定していることを強く示している。依然として強さがあり、かなり堅調だ」、「インフレを2%に戻す軌道に乗せるべく、5年間にわたって取り組んできた。一定の進展はあったが、目標の達成が必要だ。それが実現すれば、金利は引き下げられると思う」 | -------- |
| 1/14 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「この国の長期的なインフレ率にとって、FRBの独立性はこれ以上ないほど重要だ」、(トランプ政権によるパウエル議長への圧力について問われ)「中銀の独立性がないところでは、インフレは勢いよくぶり返す」、「われわれは過去5年間、インフレ率を引き下げるために闘ってきており、それは容易なことではなかった。FRBの独立性が攻撃されれば、その問題はさらに悪化する」 | -------- |
| 1/14 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「トランプ大統領が過去1年間にFRBに圧力をかけてきたのは、金利が原因だ」、「政策担当者は今年後半に再び利下げを行う可能性はあるが、今月末の次回の会合では金利は据え置かれるべきだ」 | -------- |
| 1/14 | 三村・財務官 | 「最近の為替について、経済的なファンダメンタルズを反映しているようには見えない」、「最もいけないのはボラティリティー(大きな変動)だ。円安に伴う輸入インフレのデメリットが目立つという声もいろんなところから聞こえてくる」 | -------- |
| 1/14 | 片山・財務大臣 | (足元で進む円安に)「極めて遺憾であって憂慮している。その見方については日米財務相ともに共有した」、(日本政府としては)「日米財務相共同声明の考え方を踏まえて、投機的な動きを含めて行き過ぎた動きに対しては、あらゆる手段を排除せずに適切な対応を取る」 | -------- |
| 1/8 | ミラン・FRB理事 | 「約1.5%の利下げを想定している。この想定はインフレに関する私の見解に大きく基づいている」、「基調的なインフレはFRBの目標からノイズのレンジ内で推移しており、総合インフレが中期的にどのようになるかを見極める良い示唆になっている」 | -------- |
| 1/8 | ベッセント・財務長官 | (FRB議長人事の決定時期はダボス会議)「その直前か直後になる可能性がある。1月中だと思う」、(金利は高過ぎるかとの質問に対して)、「現在の金利水準は中立金利を依然として大きく上回っている。景気抑制的なスタンスであるべきではないと考えている」、(適切な金利水準について)、「多くのモデルでは2.50−3.25%程度を示すだろう」 | -------- |
| 1/6 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「現在の金利水準が、中立と推定されるレンジ内にある」、「今後の政策運営については、2大責務の両面での進展を見極めながら、きめ細やかな判断が求められる」、「採用率が低い中で、労働市場のさらなる悪化は誰も望んでいない一方、インフレ率が目標を上回る状態が5年近く続いており、高インフレ期待の定着も避けたいところだ。まさに微妙なバランスだ」 | -------- |
| 1/6 | ミラン・FRB理事 | 「政策が中立水準付近にあるとは、かなり言いがたい。現状は明らかに景気に抑制的であり、経済の足かせになっている」、「今年は100ベーシスポイントを大きく超える利下げが正当化されると考えている」 | 株価の上昇に寄与。 |
| 1/5 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「景気の底堅さを踏まえ、今は中立にかなり近い状態だと推測される」 | -------- |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書



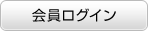
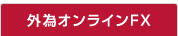
![365FX[くりっく365]](/img/tab_365_off.png)
![今日のアナリストレポート[月〜金 毎日更新]](common/img/report.svg)
![お客様サポート電話番号:0120-465-104[携帯電話・PHSからも利用可]【受付時間】午前9:00〜午後5:00(土日・年末年始を除く)](/common/img/telinfo.png)